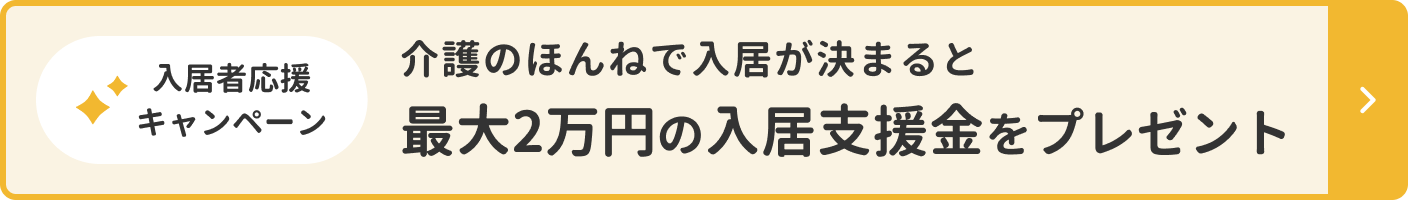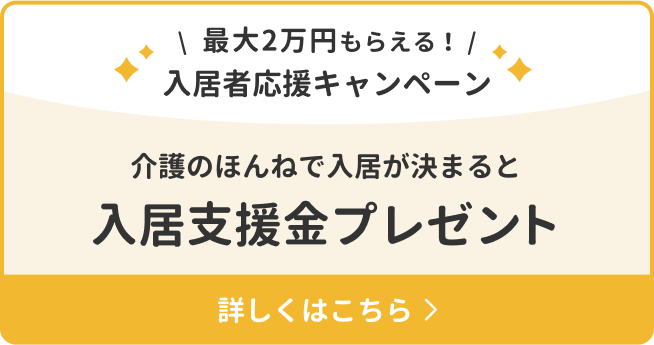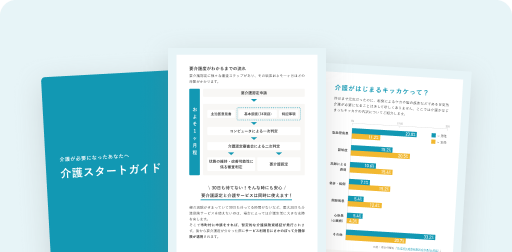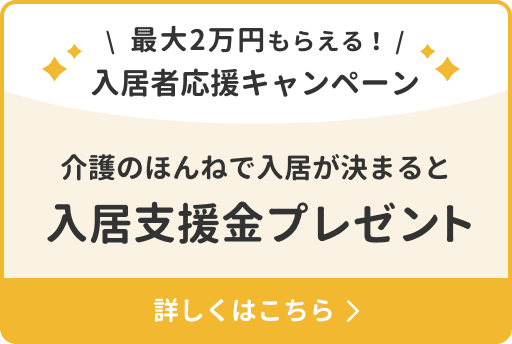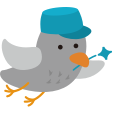訪問サービスとは|サービス内容・費用を一覧で紹介
自宅や入居している施設に介護職員が訪問し、生活の介助をしてくれるのが訪問サービスです。移動の手間を省ける、介護職員とコミュニケーションを取れるといったメリットがあります。ただし「訪問サービス」と一言でいってもさまざまな種類があります。各サービスについて詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。
訪問サービスは介護保険サービスの一部
訪問サービスは介護保険サービスの1つです。介護保険サービスとは2000年から始まった介護保険制度にもとづいてスタートしました。介護保険サービスは日本国内の高齢化が進むにつれて整備されたものです。介護サービスの費用を当人だけでなく、社会全体で支えるために作られました。介護保険を用いることで、1~3割負担で介護サービスを使えます。
介護保険サービスを使うためには2種類の条件があります。1つが「65歳以上であり要支援・要介護認定を受けていること」です。2つ目が「40~64歳で特定疾病にかかっており、要介護認定を受けていること」になります。つまりどちらにせよ要支援・要介護認定を受ける必要があります。
要支援・要介護認定とは
介護が必要になった際に受けるべきなのが要支援・要介護認定です。必要になった際は市区町村にいき、認定調査を依頼しなければいけません。認定調査員といわれる役職の人が本人に直接質問をしたり、機械による判定を受けたりしながら「介護が必要な度合い」を判断します。
その結果、要支援1~2、要介護1~5という7段階で介護の必要なレベルを判定するのです。結果によっては「自立」といって「介護が必要ない」と判断されることもあります。自立の場合は介護保険を使えません。
訪問サービスとは
要介護認定を受け、要支援もしくは要介護認定を受けたら、介護保険を用いて介護サービスを使えます。ただし一言で「介護保険サービス」といっても種類はさまざまです。実際に施設でサービスを受ける「通所サービス」や短期間だけ施設に入ってサービスを受ける「短期入所サービス」、ケアマネジャーからケアプランを作成してもらう「居宅介護支援サービス」などがあります。
なかでも介護職員や理学療法士、作業療法士などが自宅を訪れて介助やリハビリをするのが「訪問サービス」です。では訪問サービスのメリットについて詳しく紹介しましょう。
訪問サービスのメリット
移動の手間を省ける
職員が自宅を訪問してくれるので、介護対象者職員としては自宅で待っているだけでいいのがメリットです。寝たきり状態にある場合は移動が困難な場合もあります。そんなときも自宅で待っているだけでいいので、負担がかかりません。
コミュニケーションが生まれる
在宅介護を続けている場合、または要介護の方が1人で生活をしている場合はコミュニケーションが少なくなってしまうこともあります。会話を通して認知機能にも好影響を及ぼすことが分かっており、コミュニケーションが認知症の予防につながるのです。
住み慣れた自宅でサービスを受けられる
自宅でサービスを受けることで安心できる人もいます。落ち着いた心地で介護サービスを受けられるので、介護対象者に余計なストレスがかからないのもメリットです。
訪問サービスを一覧でご紹介
訪問サービスにはさまざまな種類があります。あらゆるニーズに合わせて選べるので、介護対象者や介護担当者が求めていることをもとに、ケアマネジャーと相談しながら必要なサービスを選んでいきましょう。
では訪問サービスを一覧で紹介します。
訪問介護
訪問介護は最もスタンダードな訪問サービスです。食事や入浴などの介助、家事のお手伝いなど、要介護者の身の回りの世話をしてくれます。介護職員がやってくるので、安心して任せられるのが大きな魅力です。また在宅介護の場合、介護者であるご家族が担当の方が数時間だけでも息抜きできる時間を作れます。
訪問入浴介護
「入浴」に特化した訪問サービスです。介護対象者の状態によっては、通常の浴槽での入浴が難しくなることがあります。訪問入浴介護の場合、介護職員が浴槽を持参してくれますので、安心して入浴できるさせられるのがメリットです。
訪問看護
訪問看護とは看護師などが自宅を訪問して脈拍や体温のチェック、点滴、注射などの医療措置をしてくれるサービスです。健康に不安ある方にとって、自宅にいながら医療的なケアを任せられますので、とても信頼おけるサービスといえます。
訪問リハビリテーション
訪問介護では介護職員が住まいを訪ねてくれます。訪問リハビリテーションの場合、理学療法士や作業療法士などのリハビリのプロが、住まいを訪問してリハビリの補助をしてくれるのが魅力です。
夜間対応型訪問介護
介護が必要な方の場合、夜間に体調を崩してしまう場合があります。そんなときに近くに補助ができる人がいないと対処できないこともあるのです。夜間対応型訪問介護はその名の通り、夜間でも介護職員が見守ってくれるサービスになります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
看護師や介護職員が24時間体制で介護対象者の体調の変化に備えてくれるサービスです。万が一、突然体調を壊してしまった場合などに24時間体制の専門家がすぐに駆けつけて対処してくれます。「随時対応型」とある通り、呼ばれたタイミングで対応してくれるサービスです。
訪問サービスの費用について
では、介護保険が適用されるとして、訪問サービスを利用する際の費用はおおむねどの程度なのでしょうか。厳密にいうと費用はそれぞれの状況によって違います。介護保険の自己負担額は人によって1~3割負担と開きがありますし、介護サービスにおいて金額を表す「単位」の額は市区町村によって開きがあるのです。
この記事では「自己負担額1割、1単位10円」として金額算出してみますので、ぜひ参考にしてください。
訪問介護
| サービス内容 | 時間 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 167円 |
| 20~29分 | 250円 | |
| 30~59分 | 396円 | |
| 60分以上 | 579円(30分ごとに84円加算) | |
| 生活援助 | 20~44分 | 183円 |
| 45分以上 | 225円 | |
| 通院等乗降介助 | 99円 | |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
訪問入浴介護
| サービス内容※介護職員2人でする場合 | 自己負担額 |
|---|---|
| 清拭・部分浴 | 1,134円 |
| 全身浴 | 1,260円 |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
訪問看護
| 施設種別 | 時間 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーション | 20分未満 | 313円 |
| 20~29分 | 470円 | |
| 30~59分 | 821円 | |
| 60~89分 | 1,125円 | |
| 病院・診療所 | 20分未満 | 265円 |
| 20~29分 | 398円 | |
| 30~59分 | 573円 | |
| 60~89分 | 842円 |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
訪問リハビリテーション
| 時間 | 自己負担額 |
|---|---|
| 20分以上 | 307円 |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
夜間対応型訪問介護
| オペレーションセンターの有無 | サービス内容 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| あり | 基本使用料 | 1,025円(月額) |
| 定期巡回サービス | 386円(1回) | |
| 随時訪問サービス
(訪問介護員1人) |
588円(1回) | |
| 随時訪問サービス
(訪問介護員2人) |
792円(1回) | |
| なし | 2,800円(月額) | |
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
| 訪問看護サービスができる看護師の有無 | 訪問看護サービスの有無 | 要介護度 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| いる | なし | 要介護1 | 5,697円 |
| 要介護2 | 1万0,168円 | ||
| 要介護3 | 1万6,883円 | ||
| 要介護4 | 2万1,357円 | ||
| 要介護5 | 2万5,829円 | ||
| あり | 要介護1 | 8,312円 | |
| 要介護2 | 1万2,985円 | ||
| 要介護3 | 1万9,821円 | ||
| 要介護4 | 2万4,434円 | ||
| 要介護5 | 2万9,601円 | ||
| いない(別の事業所と連携) | 要介護1 | 5,697円 | |
| 要介護2 | 1万0,168円 | ||
| 要介護3 | 1万6,883円 | ||
| 要介護4 | 2万1,357円 | ||
| 要介護5 | 2万5,829円 | ||
参考:厚生労働省「介護報酬の算定構造(R3.1.18)」
訪問サービスの導入はケアマネと相談して決める
実際に訪問サービスを利用する際には、自身の予算と負担を照らし合わせながら導入するサービスを決めましょう。そのケアプランを決めるのはケアマネジャーです。最も身近にいる専門家ですので、相談しながら金銭的にも肉体的にもストレスを軽減できる計画を練っていきましょう。
-
関東 [12234]
-
北海道・東北 [6920]
-
東海 [4898]
-
信越・北陸 [3311]
-
関西 [6708]
-
中国 [3568]
-
四国 [2056]
-
九州・沖縄 [7729]
この記事のまとめ
- 訪問サービスは介護対象者のもとに事業者が来るサービス
- 「移動する手間がない」「コミュニケーションを取れる」などのメリットがある
- 訪問サービスの導入はケアマネジャーと相談する
豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します