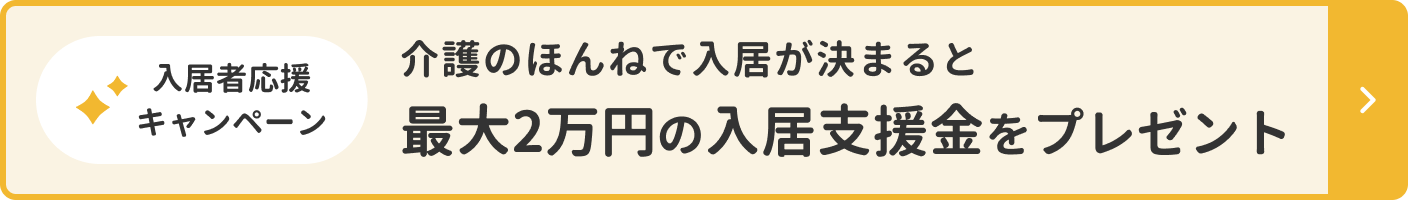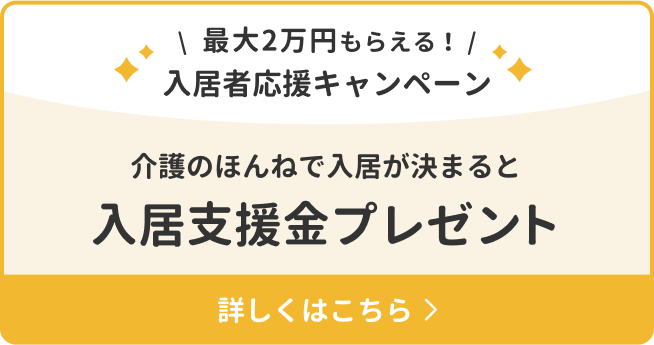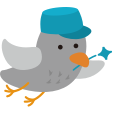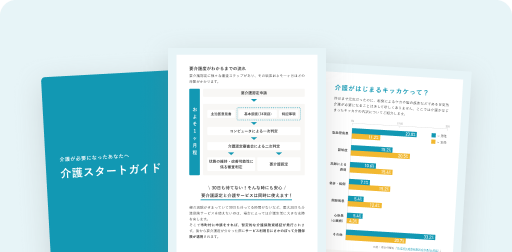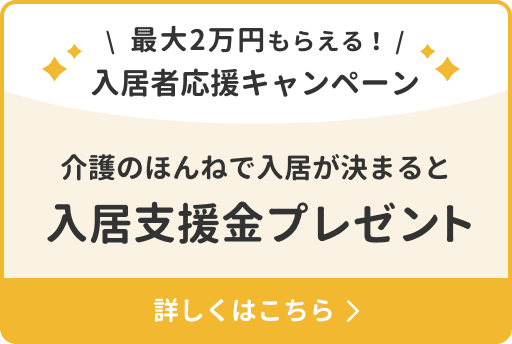高齢者におすすめの脳トレ方法はありますか?
今は健康な親ですが、今後のことを考えると認知症の予防を考える必要があると思っています。そこで認知症予防に効果的なおすすめの脳トレ方法を教えてください。
A簡単な運動から、プリントやホワイトボードを使った計算、なぞなぞ、間違い探しなど、たくさんあります。
脳トレの方法は道具がなくてもできる簡単な運動から、プリントやホワイトボードを使った計算、なぞなぞ、間違い探しなど、たくさんの種類があります。

脳トレは認知症予防にもつながります。毎日やるからこそ意味がありますので、楽しく簡単にできる方法が知りたいですよね。ここでは、いくつかの脳トレ方法を紹介していきます。自分や家族のお気に入りのトレーニングを見つけていきましょう。
高齢者の脳トレは認知症の予防につながる
年をとると物忘れが多くなり「もしかして認知症なんじゃないか……」と不安に感じたことがある人もいると思います。「自分や家族が認知症になったらどうしよう」と思ったことがある人におすすめなのが「脳トレ」です。脳トレは認知症の予防として老人ホームや病院でも多く取り入れられています。
楽しみながら考えたり覚えたりすることで脳が刺激されるので、高齢者の脳トレは認知症の予防として大きな効果を期待できます。友人や家族などと脳トレをすることで、コミュニケーションもとれて脳が活性化するのです。
笑いが生まれれば、健康になる可能性がある
笑うことによって健康になる可能性があるのも、高齢者が脳トレをおこなうメリットの一つです。大阪府立健康科学センターがおこなった研究では「ほぼ毎日笑う人」と「ほとんど笑う機会がない人」で、笑う機会がない人の方が、1年後の認知機能低下のリスクが約3.6倍も大きいという研究結果が出ています。
参考:大阪府立健康科学センター「笑いの頻度と認知機能との関連についての横断・縦断研究」また、笑いを用いた療法が持つ、高齢者のうつ症状や睡眠障がい、認知症への予防効果も期待されています。面白い脳トレを通して笑いが生まれれば、健康になる可能性があるのです。
では、高齢者の脳トレとは具体的にどんなことをするのでしょうか。道具のいらない方法や、大勢で楽しむことのできるレクリエーション型、1人の時間でも楽しめる脳トレなど、さまざまな種類があります。自分や家族にあった方法を見つけられるように、誰でも楽しめる簡単な脳トレを紹介していきます。
プリントを使った高齢者向けの脳トレ
はじめに紹介するのはプリントを使った脳トレです。印刷物を用意しておけば、1人でもみんなでもやりたい時に簡単に楽しめます。
点つなぎ
数字が書いてある点を1から順番につなげていくと、最後に一筆書きの絵が完成します。手を動かしていくことが脳への刺激となるので、数字を順番に探しながら点と点をつないでいく作業は効果的な脳トレです。最終的に浮かび上がってくる絵を考えることによって、イメージ力もアップします。
計算問題
「計算問題」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、計算問題にはたくさんの種類があります。簡単な足し算や引き算はもちろんのこと、空欄に当てはまる記号を考える「50□15=35」のような問題もあります。
高齢者にはそろばんが得意な方も多いので、楽しみながら計算問題に取り組めるのではないでしょうか。
漢字問題
魚や花などの難しい漢字の読みを考えたり、バラバラになった漢字の一部を組み立てながら、何の漢字になるかを考えたりするなど、漢字を使った脳トレは高い人気があります。
他にも四字熟語や、俳句、百人一首などを使った問題も多くありますので、好みに合わせた問題を楽しめるのが魅力です。
昭和クイズ
現在の高齢者は昭和生まれの方が大半といえます。そのため、昭和を題材としたクイズは自分の青春時代を思い出しながら楽しめるクイズです。
橋幸夫さん、舟木一夫さん、あと一人は誰でしょう?
この問題の答えは、西郷輝彦さんです。このように昔の経験や思い出に触れることは「回想法」といって、介護の現場でもレクリエーションとして取り入れられている手法です。脳の活性化も期待できるため、回想法は認知症へのアプローチの一つとされています。
都道府県当てクイズ
地域の特徴や観光名所をヒントに、連想される都道府県を答えるクイズです。
例えば「都道府県の中で人口密度が最も高い」「浅草寺や両国国技館がある」「日本の首都である」というヒントから連想される都道府県はどこでしょうか? この問題の答えは「東京都」です。
出題者がご家族であれば、過去に旅行した場所を問題にするなど、昔の楽しかった経験を思い出すきっかけにもなります。自分の記憶を思い返しながら答えられるので、回想法としても取り組めるクイズです。
ホワイトボードを使った高齢者向けの脳トレ
家族や友人たちと一緒に複数人で盛り上がる脳トレといえば、ホワイトボードを使ったものです。介護施設のレクリエーションとしてすることも多い内容ですが、自宅にホワイトボードとマーカーペンさえあれば簡単に楽しめます。
オノマトペクイズ
まずはホワイトボードにいくつかの単語を書き出します。その単語に当てはまるオノマトペをみんなで意見を出し合いながら考えていくゲームです。
風→ヒューヒュー
冬→???
「冬」と聞いて思いつくオノマトペは何でしょう? 「シーン」でも「しんしん」でも大丈夫です。決まった正解はありませんので、出た意見を書き出していきましょう。
書き出した単語のオノマトペが決まったら、書き出した単語を消します。ホワイトボードにはオノマトペだけが残るはずです。
今度は、反対にオノマトペを見て先ほど書き出した単語が何だったかを思い出すクイズをします。
自分たちで単語のイメージを想像してオノマトペを考える楽しさと、少し前の記憶を思い出す作業により脳が活性化されます。
「〇〇しい」探し
タイトルの通り「〇〇しい」の〇〇に当てはまる言葉を探すゲームです。例えば「うれしい」「たのしい」「うらやましい」などがあります。
なかなか言葉が見つからない時には「あ」から始まる言葉で考えてみましょう。「『あたらしい』はどうですか?」と提案しても大丈夫です。
「〇〇しい」という言葉が見つかったら、今度は見つけた言葉から話を聞いていきます。
例えば「たのしい時ってどんな時?」や「うれしい時の思い出はなんですか?」といった具合で質問するといいでしょう。
言葉を見つけることはもちろん、昔の記憶を呼び起して思い出しながら話すことも回想法として効果的な脳トレです。思いがけない昔の恋愛話や武勇伝が聞けて会話が盛り上がること間違いありません。
この歌なんの歌?
ある歌に出てくる言葉をホワイトボードにいくつか書いていきます。例えば「きれいな花」「扉はせまい」「腕を振って」。この時点でなんの歌か分かりますか? 正解が出てこない場合には、もう少し単語を書き出していきましょう。
出題のポイントは、少し難しい単語から書き出して、だんだんと分かりやすいヒントにすることです。すると、さまざまな答えが出てきて盛り上がります。
では、ヒントを追加していきましょう。
「しあわせ」「汗かき」「べそかき」「一日一歩」
もう分かった方も多いかと思います。答えは水前寺清子さんの『三百六十五歩のマーチ』です。
正解が出た後は、その曲を流してみんなで歌を歌うこともいいでしょう。カラオケ気分で歌うことで気分転換にもなります。
ことわざクイズ
一部を空欄にしたことわざをホワイトボードなどに書き、空欄に入る言葉を答えてもらうクイズです。
例えば「□も木から落ちる」「□の上にも三年」の□に入る言葉は何でしょうか? この問題の答えは、順番に「猿」「石」となります。
このような問題のほかにも、ことわざの状況が描かれたイラストを見せて、それをヒントにことわざを答えてもらうなど、出題の仕方もバリエーションがあります。ことわざはたくさんの種類が存在するので、出題する人も作問がしやすいでしょう。
高齢者向けの脳トレに効果的ななぞなぞ
子どもから大人まで楽しめる「なぞなぞ」も人気です。「パンはパンでも食べられないパンはな~んだ?」「フライパン!」と、道具がなくてもすぐに楽しめる遊びとして人気があります。
さまざまな種類の中から、特に脳トレに効く高齢者向けのなぞなぞを紹介します。
イメージから答えを導き出すなぞなぞ
出題者が、答えから連想するいくつかのヒントを言います。例えば「赤、白、黄色などたくさんの色があって、歌にもなっている、春に出てくるものなーんだ?」
分かりましたか? 最終ヒントは「花」です。
答えは「チューリップ」です。ヒントからイメージして、身近にあるものを思い出すことは、脳を活性化するのにとても効果があります。
テーマを「春」や「食べ物」など1つの区分に絞ることで答えが導きやすくなり、簡単に楽しめます。なかでも、季節を題材としたなぞなぞは高齢者に大人気です。
高齢者の脳トレに効果的な体操
体を動かして体操することも大切な脳トレです。しかし、高齢者となると体を大きく動かすラジオ体操などは難しい場合も多いかと思います。
そこで、座ったままでもできる、脳トレとして効果のある簡単な体操を紹介します。
指先体操
手は「第2の脳」「外部の脳」とも呼ばれます。指先を動かしておこなう指先体操は、脳を刺激する効果的な脳トレです。
指先体操の種類はさまざまですが、基本的なものだと「指先合わせ」があります。最初に親指と人差し指の指先を合わせ、その次に親指と中指、親指と薬指、親指と小指というように、順番に違う指どうしを合わせていく体操です。
指先体操には、動作がシンプルなものから難しいものまで存在し、おこなう動作が難しくなるほど、脳の活性化が期待できます。
指折り体操
指を1つずつ折りながら1~10まで数えていく指の体操です。
まずは両手を胸の前でパーにします。次に両手の親指を曲げながら数を数えていきます。1で親指、2で人差し指。5の時には、左右ともにグーの状態です。続いて、6は小指を上げます。そこから順に一つずつ指を開いていき、10になると両手がパーの状態に戻ります。
高齢者にとって、指を1つずつ動かすことは難しいのでゆっくりとおこないましょう。その後、少しずつスピードアップすることで、脳に刺激を与えられます。
簡単な体操なので、脳トレ前の準備体操として毎日取り入れるのもいいでしょう。
足踏み体操
こちらも座ったままできる体操です。まずは声に出して数を数えながら、椅子に座ったまま足踏みをして、歩くときのように腕も振ります。この時に腕と足が同じにならないようにしましょう。歩く時のように、右腕を振るときには左足が動くはずです。
足踏みに慣れてきたら、次は「3の倍数」で手拍子をします。このときに注意したいのは、3の倍数で手拍子しているときでも、足踏みは続けることです。1~30までの数で挑戦してみましょう。
3の倍数なので、右腕、左腕を振ったら手拍子、となります。はじめはできなくても、リズムさえつかめば思ったよりも簡単にできます。
3の倍数に慣れてきたら「3と5の倍数」にも挑戦してみてください。
足踏み体操は、数を数えながら頭、口、腕、足を一度に動かすことができ、脳トレとして効果のある体操です。足を動かすことで、簡単な筋トレにもなり転倒防止にもつながります。
間違い探しで脳トレ
2つの絵を見比べながら、違っている箇所を探す間違い探しは、高齢者でも気軽に楽しめる脳トレとして人気です。
瞬時に絵を記憶し、観察力を使って間違いを見つけようとすることで脳が刺激されます。漢字や計算などの脳トレに難しそうなイメージをお持ちの高齢者の方でも、イラストや写真があることで取り組みやすく、ゲーム感覚できるオススメの脳トレです。
イラストだけでなく、漢字を使った間違い探しもあります。
例えば、
赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤示赤赤赤
さて、間違いはどこにあるでしょう?
答えは2列目の右から4番目。「赤」の文字の中に一つだけ「示」という漢字が混ざっています。
このように漢字を使った間違い探しもありますので、たまには上級編として楽しむのもいいでしょう。
施設のレクでも使用されている手遊び
手指を動かすことは脳の活性化を促すので、手遊びは高齢者の脳トレにも効果的です。手のひら全体を使うものや、指先を使うものなど、いろんな種類があります。
実際に施設のレクリエーションとしても使われていることが多い手遊びを紹介します。
でんでん虫
多くの方が知っている童謡を使った手遊びです。まずは、片方の手をチョキにして、もう片方の手でグーを作ります。そして、チョキにした手の上にグーの手をのせて、かたつむりを作りましょう。
このかたつむりを、今度は反対の手にチェンジします。最初に左手がチョキだったならグーにして、グーだった手をチョキにします。
これを「でんでんむしむし かたつむり おまえの目玉はどこにある つのだせ やりだせ 目玉だせ」の歌に合わせて、かたつむりを交互に作り直していくという手遊びです。
歌を歌いながら、両手を同時に動かすので脳トレに最適です。はじめはゆっくり手を入れ替えていき、慣れてきたら少しスピードを上げて手を入れ替える回数を増やしていくとおもしろいですよ。
後出しジャンケン
後出しジャンケンは「ジャンケンポン・ポン」と一拍遅れて手を出す遊びです。後出しをした側が勝つのを目指すパターンと、負けなければいけないパターンがあります。
レクリエーションで楽しく認知症予防を
認知症予防に効果的な脳トレにはたくさんの種類があります。道具がいらない体操や、なぞなぞ、手遊びの脳トレは気軽にいつでも楽しむことができます。
ホワイトボードやプリントを使った脳トレは、ご家族やお友達とコミュニケーションを取りながらおこなってみましょう。
毎日の習慣として、意識的に脳トレをすることは健康を維持していくために重要です。年をとるにつれ、自分が思っているよりも体は老化していきます。散歩など、体を動かすことも大切ですが、毎日はなかなかできなかったり、体力的にも辛かったりする人も多いかと思います。
脳トレは、どんな方でもチャレンジできるリハビリです。脳を活性化させるだけでなく、体を動かすことで筋肉を鍛えることにもつながります。また、「コグニサイズ」といって「運動」と「認知課題」の両方に同時に取り組むとさらに効果的です。前述した「足踏み体操」の3の倍数や、3と5の倍数で手を叩くという行為はコグニサイズにあたります。
ぜひ、ご自身や家族が楽しいと感じる脳トレを見つけて、毎日の習慣に取り入れてください。
-
関東 [4771]
-
北海道・東北 [2431]
-
東海 [1651]
-
信越・北陸 [1002]
-
関西 [2392]
-
中国 [1153]
-
四国 [722]
-
九州・沖縄 [2389]

介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、認知症ケア上級専門士、認知症介護実践リーダー、米国アクティビティディレクター、他。介護職として働く傍ら、レクや認知症、コミュニケーションに関する研修講師も務める。2014年米国アクティビティディレクター資格取得。レクリエーションを通じ、多くの高齢者に「人と触れ合う喜び」を伝え、「介護技術としてのレクリエーション援助」を広める一方、介護情報誌やメディアにおいて執筆等を手掛けている。『認知症の人もいっしょにできる高齢者レクリエーション 』(講談社)など著書多数。
豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します

 0120-002718
0120-002718