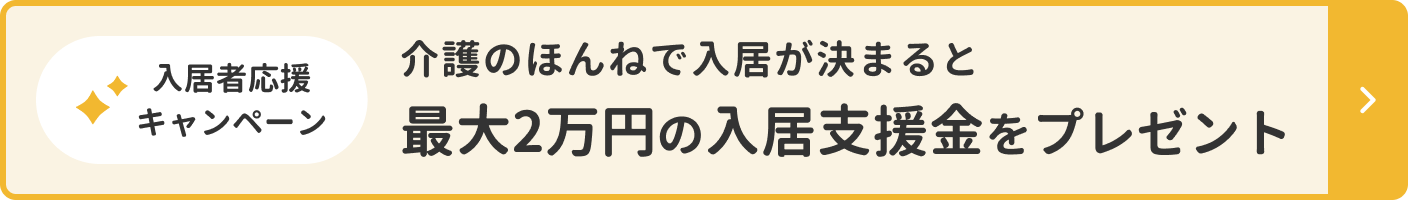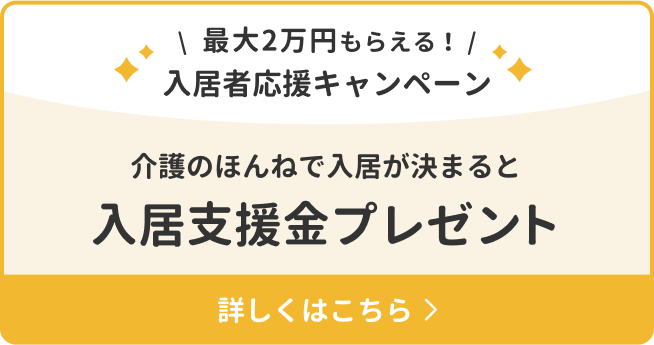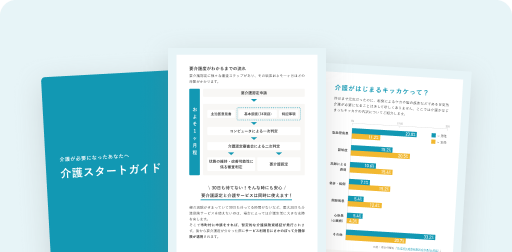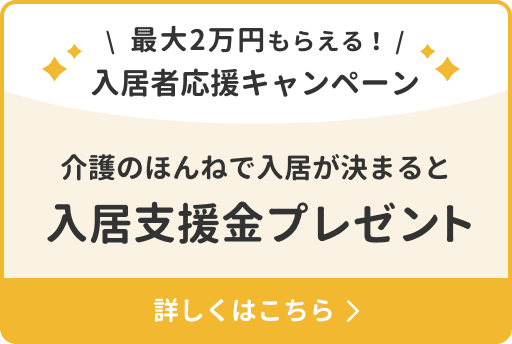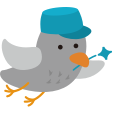インシュリン投与とは|投与の方法・利用可能な施設などを紹介
インシュリンの投与は糖尿病の患者に対しておこなわれる医療措置です。インシュリン製剤を皮下注射することで上がりすぎた血糖値を下げ、糖尿病による合併症を防ぎます。 医師の指導を受ければ自己注射も可能ですが、できない場合は医師・看護師がおこないます。
今回はインシュリンの投与についての概要、糖尿病の症状、対応可能な介護施設の探し方などを紹介します。

インシュリンとは「血糖値を下げる効果のあるホルモン」
インシュリンとはホルモンを指します。血糖値を下げてくれる効果があり、本来は体内で作られます。インシュリンの分泌量が減少した際には、注射などでインシュリンを投与しなければ血糖値が下がらなくなってしまうのです。
インシュリンの働きは「ブドウ糖をエネルギーに変えること」
インシュリンは主に糖分を含むものを摂取した際に働くホルモンです。炭水化物などは摂取すると体内で消化酵素によりブドウ糖になります。その後、ブドウ糖が小腸から吸収されて血管に吸収されるのです。この時点では当然、血糖値が高い状態にあります。
そこで血糖値を下げるために、膵臓で作られたインシュリンが分泌され、ブドウ糖を筋肉などに行きわたらせ、エネルギーに変えてくれるのです。つまりインシュリンが分泌されないと血液中の糖は残存してしまうことになります。
血糖値が高まったら身体にどんな異常が起きるのか
血糖値が高い状況だと体にどんな悪影響があるのでしょうか。血中のブドウ糖が多いとそのぶん血液の流れが悪くなってしまいます。血液は身体全身に栄養を溶ける役目があるので、スムーズに流れないと栄養が行き渡りません。
血液が循環しないこと、またはブドウ糖がエネルギーにならないことで身体が不調になってしまいます。体力が著しく低下したり、喉が渇きやすくなったりします。最悪の場合、失明や腎不全などといった重大な体調の悪化につながってしまうのです。
この高血糖である状態のことを「糖尿病」といいます。
糖尿病の症状とは
血糖値が高くなって糖尿病を引き起こすと「疲れやすい」「体重が減る」「喉が渇く」などの症状が起きるようになります。
糖尿病で疲れやすくなるのは「身体がきちんと血糖を使えないから」
糖尿病によって疲れやすくなる理由は「適切にブドウ糖をエネルギーとして変換できなくなるから」です。身体が必要とするエネルギーの量をしか摂取はしません。しかしインシュリンが足りないので、エネルギーは基準値以下になってしまいます。その結果、疲れやすくなるのです。
糖尿病で体重が減るのは「ブドウ糖以外の脂肪やタンパク質をエネルギーとして使うから」
糖尿病になるとブドウ糖をエネルギー源として使えません。その結果、もともとある脂肪やタンパク質をエネルギーにしてしまうので、過剰にカロリーを消費し、体重が落ちていきます。
糖尿病で喉が渇くのは排尿の回数が増えるから
糖尿病になると、血液中に糖がいっぱいになってしまい、すべて吸収することが不可能になります。その結果、身体は溢れた糖を排出することになり、頻尿の状態になった結果、脱水を起こすのです。
糖尿病になった際に「インシュリン注射」が必要になる
膵臓で満足なインシュリンを分泌することが不可能になった際に「インシュリン注射」が必要になります。外部から注射によって体内にインシュリンを取り込むことで、ブドウ糖をエネルギーに変える機能を補うのです。
インシュリン注射によって血糖値が下がることにより、体内でのインシュリン分泌機能が回復することもあります。ただし膵臓の機能が正常である若いうちでなければ、なかなか機能が回復することは望めません。
インシュリンには5種類! 患者の状態によって医師が判断する
インシュリンには下記のように5つの種類があり、個人の生活スタイルや病気の状態によって選んだり、組み合わせたりして使用します。
| インシュリンのタイプ | 特性 |
|---|---|
| 超速効型 | 10〜20分で効きはじめ、3〜5時間ほど持続。食直前に投与 |
| 速効型 | 30分〜1時間で効きはじめ、5〜8時間ほど持続。食前に投与 |
| 持効型 | 24時間またはそれ以上作用 |
| 中間型 | 30分〜3時間で効きはじめ、18〜24時間ほど持続 |
| 混合型 | 超速効型や速効型に、一定量の添加物を加えたり中間型を組み合わせたもの |
インシュリン注射が必要な方が介護施設に入居する場合
糖尿病の場合、インシュリン注射は高頻度になります。例えば中間型の場合は毎日の朝食前に、混合型の場合は朝と夕食の前に投与が必要です。ですので、老人ホームをはじめとする介護施設への入居を考えている方は、インシュリンの処置ができる施設を探す必要があります。
では介護施設での暮らしに関して、インシュリン注射で気をつけておくべきポイントを紹介しましょう。
インシュリンを投与できるのは看護師か自分自身
介護のケースでインシュリンを投与できる職員は限られています。介護士は投与ができません。医師からの指示に従って看護師が注射をすることになります。ですので、24時間にわたって看護師が常駐している施設を選ぶ必要があります。
ただしインシュリンは、自身で投与する「自己注射」も可能です。この場合、あらかじめ医師からの指示を受けたうえで、正しい箇所に正しいタイミングで投与しなければいけません。
自己注射をする場合は、看護師がいなくてもインシュリンの投与ができます。
自己注射での注意点
自己注射をする際にはあらゆる注意点があります。
自己注射をする際に注意したいこと
- 医師の話をよく聞いて「いつ・どこに注射するのか」を把握する
- インシュリン製剤は開封前は冷蔵庫、開封後は常温で保存をする
- 注射器は清潔な場所で保管をする
- 注射をする前に注射器の取り扱い方(空打ちや単位セット)について熟知しておく
- 注射をする場所は上腕かおなか、お尻、太もものいずれか(各々で違う)
- 注射箇所は毎回少しずらす
インシュリンは自分で投与できるので、柔軟に治療ができます。しかしその分、リスクもありますので、あらかじめ医師の話をよく聞いて、注射をするようにしましょう。
インシュリンの利用に適した施設
もし自己注射ができない場合は、介護施設の選択肢が狭まってしまいます。24時間看護師がおり、投与をしてくれる施設を探さなくてはいけません。細かい対応の不可は施設によって違いますが、施設種別で分けると以下のような受け入れ体制レベルになります。
| 介護付き有料老人ホーム | 住宅型有料老人ホーム | 健康型有料老人ホーム |
|---|---|---|
| △ | △ | △ |
| サービス付き高齢者向け住宅 | グループホーム | 軽費老人ホーム・ケアハウス |
| △ | △ | △ |
| 特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 |
| △ | ◯ | ◯ |
インシュリンの副作用・低血糖についてあらかじめ知っておく
インシュリンには副作用もあります。それが「低血糖」です。インシュリンが効果を発揮しすぎたあまり、高血糖から低血糖になる可能性があります。糖尿病も命の危険がある疾患ですが、低血糖もまた最悪の場合、死に至ります。
低血糖の症状には「軽度」と「重度」のものがあります。軽度の低血糖だと「発汗、ふるえ、動悸」などを引き起こし、重度になると「めまい、倦怠感、脂汗、かすみ目」などの症状が発生するのが特徴です。
低血糖になってしまった際の対処法
低血糖を自覚した際はすぐに「ブドウ糖」を摂りましょう。ブドウ糖は粉末タイプで市販されているものもあります。もし持っていなければブドウ糖が含まれている清涼飲料水を飲んでください。比較的、甘味の強い飲料を選ぶといいでしょう。
多くの場合、ブドウ糖を摂取すれば症状は落ち着きますが、もし15分たっても症状が治まらない場合は再度同じ物を摂取しましょう。
インシュリン注射が必要な際の介護施設探しは慎重に
介護職員は医療行為にあたる注射をしてはならないため、自己注射ができない方が入居できるのは、24時間看護師が常駐する施設に限られます。ただし、以下のような場合は応相談または受け入れ可という施設も比較的多数見られます。
インシュリン注射が必要な方を受け入れやすい介護施設
- 注射の時間帯と看護師の勤務時間が重なる
- 通院ができる
- 医師や医療機関との連携体制が整っている
自分で定期的に通院でき、薬の管理・投与ができれば、ほとんどの施設が利用可能です。注意する点としては、加齢や健康状態の悪化などの理由から自己注射ができなくなったとき、施設を退所しなければならない場合もあるということ。入居の際にはこのような事態を想定して、施設側と話をしておきましょう。
-
関東 [2217]
-
北海道・東北 [215]
-
東海 [379]
-
信越・北陸 [90]
-
関西 [1114]
-
中国 [91]
-
四国 [53]
-
九州・沖縄 [206]
この記事のまとめ
- インシュリン投与は糖尿病の患者を対象にした医療措置
- 個人に合わせてさまざまなタイプがある
- 自己注射ができなくなると施設退所の可能性もある
豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します