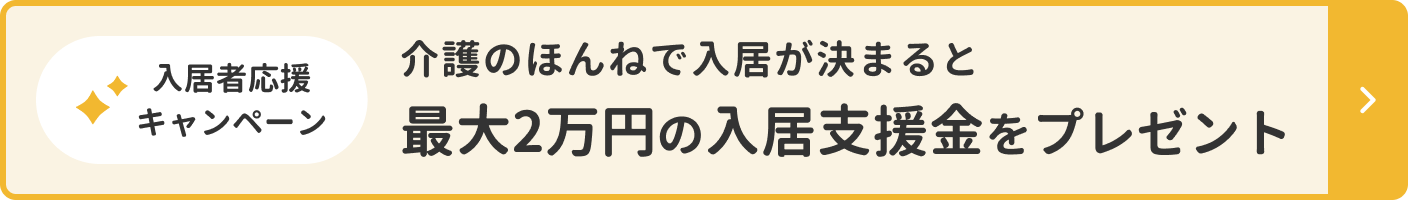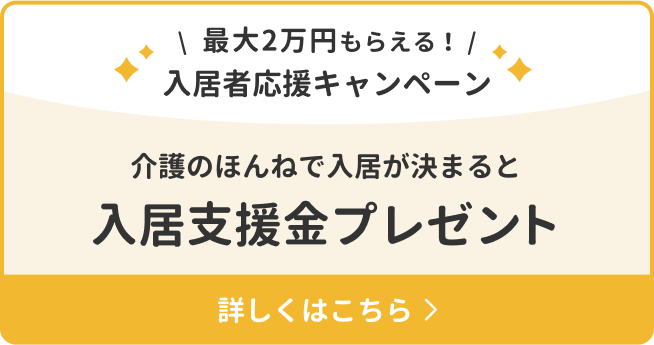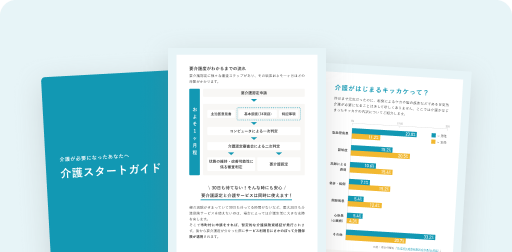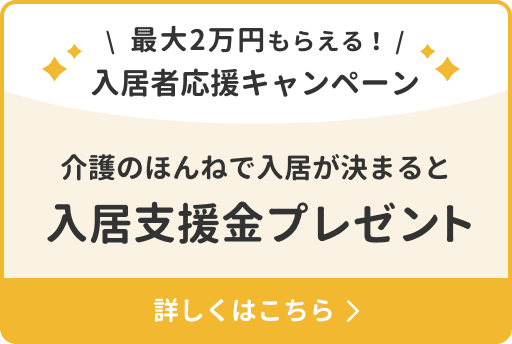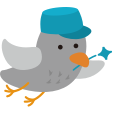嚥下障害とは|原因や食事の工夫、治療法、リハビリなどをご紹介
嚥下障害とはものをうまく飲み込めなくなってしまう症状を指す言葉です。高齢化や認知症などによっても引き起こされてしまいます。嚥下障害になってしまうと、食事そのものへの意欲がなくなり体重自体が減ってしまう恐れも有るのが特徴です。ですので、早めに対処をしなくてはいけません。
今回は嚥下障害について症状や原因、治療法、看護計画の立て方などについて解説します。


大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。
嚥下障害とは「飲み込みにくくなること」
嚥下障害は、食べ物を飲み込み胃に送る動作が難しい症状を言います。
うまく飲み込むことができないと、栄養を体内に送ることができません。低栄養や脱水、さらには食べ物を飲み込めずに窒息する危険性があります。症状が悪化してしまうと、誤嚥性肺炎という命にかかわる病気へと発展する可能性もあるので注意しましょう。
嚥下障害の症状は、大きく分けて5つあります。
食事の際にむせてしまう
水分と固形物が一緒になっている食べ物を取り入れるとむせてしまいます。食事だけではなく、自分の唾液でむせてしまうこともあるので、注意が必要です。
また、むせるのが嫌だからと言って、固形物ばかり取ることで水分不足になりやすくなります。
噛めなくなる
特に硬い食べ物は、よく噛まないと喉に詰まらせてしまいます。噛みづらくなってくると、柔らかいものを好んで食べるようになります。こうした食事ではバランスが偏ってしまい、栄養不足にもつながります。
食事を完食できない
むせたり噛むことができず喉に詰まらせてしまったりすることで、食べることへの恐怖を感じ本来の楽しみをなくしてしまいます。食事は楽しい時間であるはずが、こういう状況になってしまうと食事で苦痛を感じることになります。
出されたメニューを完食できずに終わってしまい、十分な栄養が取れないケースも多いのです。
声が変化する
嚥下障害は、声質にも関係してきます。 特に飲み込んだあと声がかすれてしまう、痰が絡みやすくなりガラガラした感じになるのが特徴です。
体重が減少してしまう
食事の量が減れば、必然的に体重が落ちてしまいます。食事のバランスも悪くなるので、体調不良を引き起こしやすくなります。
嚥下障害の原因は加齢・関連の疾患などさまざま
食事は何よりも楽しみの1つで、生きるためには欠かすことのできないものです。しかし、嚥下障害が発生してしまうと飲み込むことや噛むことが困難になってしまうため、食事の楽しみも失ってしまいます。
こういった弊害を生む嚥下障害の原因は3つあります。ここからは、3つの原因について紹介します。
年齢
年齢を重ねるごとに、噛む、飲む、食べるために必要な筋力が弱くなっていきます。そのため、食べやすい大きさにかみくだけなかったり、口を閉じることができず鼻腔内に食べ物が入っていったりするといった現象が起こります。
段階的に嚥下への不調が起こり、嚥下障害が発生する可能性が高くなります。
関連疾患
痛みや形状異常の疾患
口内炎や扁桃炎ができると、のどの痛みが発生し飲みづらさを感じます。 さらに、舌がんや咽頭関連のがんになることで、嚥下困難に陥ることもあります。
脳卒中
脳が病気によって損傷し、その障害として引き起こることがあります。
神経筋疾患
神経筋疾患は、神経の伝達がうまくいかなかったり、神経と筋肉との連携が働かなくなったりする病気です。嚥下に必要とされる筋力や反射神経が鈍くなってしまいます。これによって、嚥下障害が発生します。
認知症
脳の萎縮によって引き起こされる認知症は、中期以降になると食事の中止やせきなどの症状が出てきます。
心の問題にも関係が
嚥下障害は、病気によって発生することが多いですが、心因的要因で起こる場合もあります。代表例は、神経系によって引き起こされる食欲の低下や、ストレスによる胃炎などです。これらが原因で飲み込みづらさを感じることがあります。
嚥下障害による「誤嚥性肺炎」とは
自分の唾や食べ物を飲み込む際に、気道に間違えて入ってしまうことを誤嚥といいます。一般的には、食べ物が詰まると反射で外に出そうとする神経が働く仕組みになっています。誤嚥性肺炎は、この反射が鈍って働かなくなり、肺の中で起こる炎症のことです。
多くの場合、噛む力や舌の筋力が低下することで引き起こされます。70歳以上で肺炎を発症している方のうち、約80%が誤嚥性肺炎だといわれています。
口からものを入れるときだけではなく、直接胃にチューブを入れながら栄養を取り入れている胃ろうの人も起こるので注意が必要です。
原因としては口腔内が清潔に保たれていないことが考えられます。喉の粘膜についた細菌が、唾液や胃・食道からの逆流物と一緒に気道に入り、肺炎になってしまうのです。
一度、誤嚥性肺炎になると、反射するまでの時間が遅くなってしまうため、その後も肺炎になるリスクが大きくなります。「熱がある」「膿のような粘り気のある痰が出る」といった場合には、肺炎を発症している可能性があるので、注意しましょう。
さらに「元気がない」「日中ぼーっとしている時間が多い」「食事をするのに時間がかかる」といった症状があるときには、誤嚥性肺炎の可能性があるので医療機関へ相談しましょう。
嚥下障害の治療は「手術」と「リハビリ」
嚥下障害を改善するには、手術とリハビリの2種類があります。高齢者の場合、多くの方がリハビリを選択し症状改善をしています。具体的にどのようなことをおこなっているのか、詳しくみていきましょう。
食事介助
食事で一番注意しなければいけないことは、症状にあった形状を選ぶということです。
飲み込みできる大きさ、硬さがどのくらいなのかを把握して食事を作る必要があります。
飲み込みだけでなく噛むことに支障があるという方には、小さく切って食べさせてあげることで窒息をする危険を防げます。
リハビリ
リハビリには、間接訓練と直接訓練の2種類があります。 それぞれどういったリハビリをするのか、紹介していきます。
間接訓練
間接訓練は、食べ物を使わずにおこなう訓練のことです。食べる前に行うことで、効果をより引き出すことができます。唇、頬、舌の訓練
舌を出したり、頬に空気を入れたりすることで口腔周辺の筋力を高めることができます。
発生練習
声を出すところと食べ物を飲む場所は同じ器官です。パ行、ラ行、タ行、カ行、マ行を口に出して発声練習をすることで器官を強化できます。
呼吸筋を鍛える
気管に入りこんだ異物の排出をスムーズに行うために、呼吸筋を鍛えましょう。複式呼吸にすることで、横隔膜を鍛えることができるため、呼吸しやすくなります。
姿勢は正しく
食べるときに姿勢が悪いと、食べ物の通り道が正しく確保できないため、誤嚥を引き起こすきっかけになります。最低20分は正しい姿勢で食事ができるように練習します。
リラックスする
上半身を中心にストレッチをすることで、首や肩の凝りをほぐすことができます。凝り固まっていると、筋肉がうまく作用せず嚥下しづらくなってしまいます。
感覚を高める
口腔内を洗浄する際に、アイスマッサージで刺激をして今までのような感覚を取り戻すようにしていきます。
直接訓練
実際に食べ物を用いておこなう訓練です。段階を踏み、柔らかい食べ物から徐々に硬いものへと変化させた食事を訓練します。
食事の形を変える
本人の食べる能力に応じた食事形態にしていきます。ゼリー、ゼラチンといった柔らかいものから始め、徐々に今まで通りの食事へと段階的に引き上げていきます。 誤嚥を最小限に抑えながら食事訓練をすることが大事です。
嚥下訓練
食事をする際に一度飲み込んだあと唾液を複数回飲む訓練をします。この訓練をすることで、咽頭に食べ物が残っている状態を回避できます。
そのほか、形の違う食べ物を交互に取り入れるのも、方法の一つです。形状が違うため、口腔内や咽頭に食べ物が残ってしまうことを防げます。
嚥下障害の治療の際には看護計画を
嚥下障害がある方への看護目標は合併症を引き起こさないこと、安全にそして楽しく食事をして栄養分をしっかりと取り入れること、口腔内を清潔に保ち感染を防ぐということです。
可能な限り口から栄養分を取り入れることができるように、個々に看護計画をしっかり立て必要な場合には、援助をしてもらうことが大切になります。
看護計画は下記の項目が参考になるでしょう。
OP(観察項目)
- バイタルサイン(血圧、脈拍、体温、SPO2)
- 体重
- 呼吸状態(肺雑、喘鳴、呼吸数、痰の量や性状)
- チアノーゼの有無(顔色、四肢冷感)
- 意識レベル
- 食事、水分摂取量、咀嚼の状態
- 嚥下障害の症状(むせ、咳込み、嗄声など)の有無
- 口腔内貯留物の有無
- 食事に対する不安や意欲、食欲の有無
- 嘔気、嘔吐の有無
- 臨床検査(低栄養状態や感染の有無)
- 胸部X線など
TP(ケア項目)
- 正しい姿勢をとる
- 痰が貯留している場合は喀痰させるか、吸引により痰を除去する
- 意識がしっかりしているか、覚醒しているかを確認する
- 適切な食事の種類を選択する(とろみをつける等の工夫をする)
- 食事に集中できるよう環境を整える
- 吸引器を準備しておく
- 食事介助の際は、食べる量や速さに注意しゆっくり介助する
- 口腔内を清潔にする
- 必要時、言語療法士による嚥下訓練を依頼する
EP(教育・指導項目)
- とろみをつけたり、半固形のものを選択するなど、食事の内容を工夫するよう指導する・一口の量は少なめにし、ゆっくりと摂取するよう指導する
- 口腔内を清潔に保つよう指導する
嚥下障害の予防法とは
嚥下障害を予防するには、根本的な問題を解決、予防することも重要ですが、食事や衛生面での管理も重要になります。嚥下障害の予防方法について、紹介していきます。
食事形態に配慮する
本人が飲み込みやすいように形を変更した食事のことを嚥下食といいます。ゼリー状、ムース状などの見込める状態によってレベルが異なってきます。現状、どこのレベルにいるのか確認し、個々にあった食事を提供しましょう。
小さくカットする
噛む力が弱い、支障が出ている場合には、噛み切れる大きさに最初からカットしておきましょう。大きさを気にせずにそのまま提供してしまうと、咽頭につまり窒息してしまう恐れがあるので注意が必要です。
食事に集中する
噛むことや食材の味を楽しむということに集中しないと、誤嚥を引き起こしてしまいます。 食べることを意識させるためにも、食事の際はテレビを消すといった環境を整える工夫が必要になります。
姿勢は正しく
食事をするとき、以下の点に注意し正しい姿勢を保つようにしましょう。
- なるべく垂直に座るようにする
- 背筋を伸ばし、猫背にならないように注意
- 首を前の方向に向けて摂る
- 食べ物を飲み込む際には、顎を引くようにする
- 食後はすぐに横にならない(逆流を防止するため)
よく噛み、飲み込んでから次へ
口のサイズに合った量にし、ゆっくりよく噛むことが重要です。 特に、汁気の多い食べ物はむせてしまう可能性が高いため、スプーンで一口ずつ用意してあげましょう。 さらに、口の中に入っている状態で次の食べ物を入れるのではなく、必ず食べ終わったことを確認してから次を口に入れましょう。
口腔内を清潔に
口の中を綺麗に保つことで、歯周病、細菌による肺炎を引き起こしにくくなります。
特に寝ているときに唾液は気管に流れ、誤嚥することで誤嚥性肺炎を引き起こす可能性もあります。口腔内を清浄にしておけば、誤嚥性肺炎へのリスクを抑えることができるので、意識した生活をしましょう。
食事をしたあとは、きちんと歯磨きをして清潔にしておくことがポイントです。
舌や口の粘膜洗浄方法
- 舌を前に出し、柔らかい歯ブラシを使って奥から手前にむかって優しくこする。
- 頬の内側は、上下に優しくマッサージするようにこする。
- 舌の下は、ガーゼをまいたブラシを奥から前に向かって優しくふき取る。
上記の手順で洗浄することで、口腔内を綺麗に洗浄することができます。
普段から生活を見直して嚥下障害を予防する
人間にとって食事は楽しく、喜びの時間でもあります。食事を口からとるというのは、一見当たり前のことですが、年齢を重ねることで色々な機能が衰えてしまいます。普段の生活から意識しないと、今までできていたことができなくなることもあるのです。そして、取り戻すまでには時間と努力が必要になります。
食べることをずっと楽しく喜びに感じられるように、嚥下障害にならないよう予防していきましょう。
-
関東 [1859]
-
北海道・東北 [177]
-
東海 [295]
-
信越・北陸 [71]
-
関西 [631]
-
中国 [72]
-
四国 [46]
-
九州・沖縄 [165]
この記事のまとめ
- 嚥下障害の症状について
- 嚥下障害による「誤嚥性肺炎」とは
- 嚥下障害の治療方法
豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します