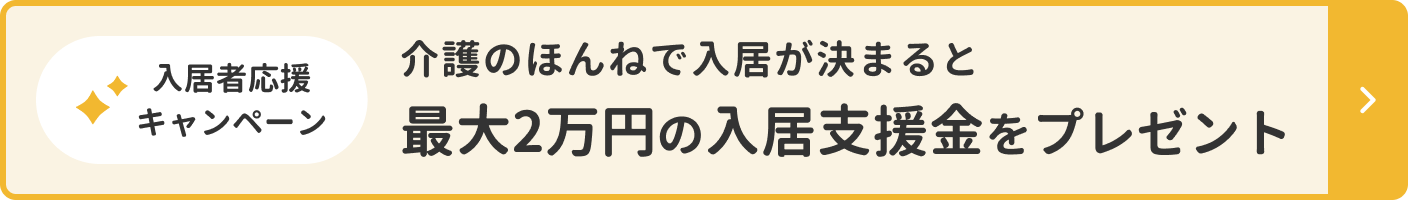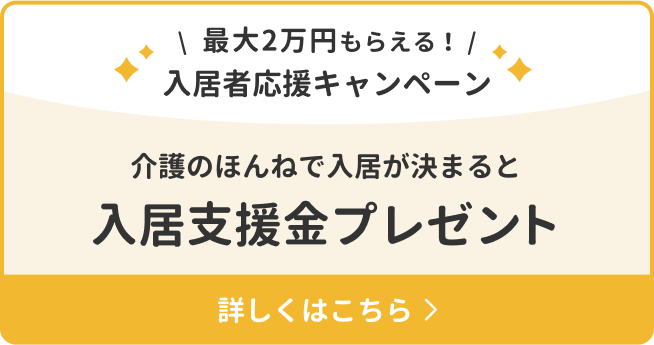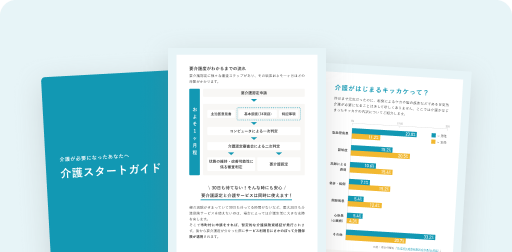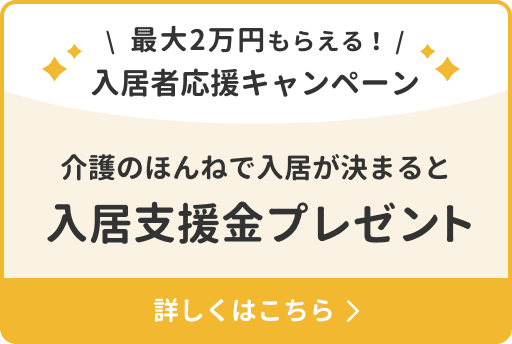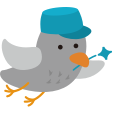【評価項目・点数あり】MMSE(ミニメンタルステート検査)とは|質問項目・カットオフ値の見方など
「家族が認知症なのではないか」と不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、自分だけでは認知症かどうかを判断できないため、答えを出すためには病院でしっかりとした検査を受けることになります。
MMSEは病院で一般的に使われている認知症の評価スケールです。今回は、MMSEという検査についてどのような検査なのか、点数のつけ方やカットオフの見方などを詳しくご紹介していきます。


大手介護専門学校にて教職員として12年勤務し、約2000名の人材育成に関わる。その後、その経験を活かし、認知症グループホームや訪問介護、サービス付き高齢者向け住宅などの介護事業や、就労継続支援B型事業所や相談支援事業所などの障がい福祉事業を運営。また一般社団法人日本介護協会の理事長に就任し、介護業界の発展を目指して活動中。
MMSE(ミニメンタルステート検査)とは
MMSEとは、「Mini Mental State Examination(ミニメンタルステート検査)」の略語です。1975年にアメリカのフォルスタイン夫妻が開発したもので世界中で最も多く用いられている認知症の検査です。2006年に、公益財団法人脳血管研究所教授・杉下守弘先生による日本語版が作成されてから日本でも広く使われるようになりました。
MMSEは特にアルツハイマー型認知症の疑いがある場合に多く用いられています。ただし、アルツハイマー型以外の認知症のスクリーニング検査としても有効です。
MMSEはあくまで「スクリーニング検査」
ただし、MMSEはあくまでもスクリーニング検査です。MMSEだけで「認知症である」と断定することはできません。「認知症の疑いがある」にとどまります。可能性がある場合は脳の検査や生活状況、本人や家族からの現在の状況の聞き取りなどを総合的に勘案したうえで認知症の診断が出ます。
自分で実行せず医療機関で診断してもらう
MMSEは簡易的にできますが、家族と本人だけで実践するのはおすすめしません。認知症の自覚がない場合、本人の自尊心を大きく傷つけてしまう可能性があるからです。
MMSEを実行するにあたっては、家族だからといって無遠慮になってはいけません。必ず専門家に相談したうえで実施しましょう。
MMSEは保険適用(3割負担)で240円で実践できる
MMSEは医療機関で検査可能です。2018年に実施された診療報酬の改定によって保険診療可能な検査としても認定されました。そのため、医療機関でも取り組みやすい検査となりました。
医療機関でMMSEを受ける場合に実際にかかる診療報酬は、80点です。これは、MMSEがそこまでの労力を要さない簡易検査となっているためです。80点は通常800円ですが、保険適用となるので3割負担の場合240円、2割負担の場合160円、1割負担の場合には80円とリーズナブルに検査を受けられます。
家族との人間関係を壊さないようにするためにも、認知症の疑いがあるからといって自分で検査しようとせずに、しかるべき機関で検査を実施するようにしましょう。また専門機関で受けたほうが正しい評価を把握できます。
MMSEの評価項目
| No | 設問内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 日時等に関する見当識 | 5点 |
| 2 | 場所に関する見当識 | 5点 |
| 3 | 言葉の記銘 | 3点 |
| 4 | 計算問題 | 5点 |
| 5 | 言葉の遅延再生 | 3点 |
| 6 | 物品呼称 | 2点 |
| 7 | 復唱 | 1点 |
| 8 | 口頭での3段階命令 | 3点 |
| 9 | 書字の理解、指示 | 1点 |
| 10 | 自発書字 | 1点 |
| 11 | 図形の描写 | 1点 |
| 合計 |
|
|
MMSEの評価項目は、全部で11問用意されています。主に質問形式となっていますが、最後の2問は文章や図形を記載する自由記述式です。ここからは、各設問にどのような評価・意味があるのか紹介していきます。
設問1:日時等に関する見当識
アルツハイマー型の認知症に多い日時などの見当識障害を判断するための設問です。「現在が何年であるのか」「今の季節は何か」「今日は何曜日か」「今日は何月何日か」を具体的に聞くことで評価します。それぞれ答えられれば得点は1点ずつ加算されます。
設問2:場所に関する見当識
設問1に続けて見当識障害があるかどうかの評価です。見当識障害は日時だけでなく「場所」に関しても起こります。「現在いる病院」や「診療所の名前」が言えるかどうか、所在地に関することをある程度認識しているかどうかで判断します。
設問3:言葉の記銘
記憶には、記銘・保持・想起という3つの段階が存在しています。この設問では短時間で言葉を記銘することができるかどうかの評価が可能です。
設問4:計算問題
脳内における記憶力に関する評価と、記憶された情報に対してどのように作動できるかを判断する設問です。情報を脳が正確に取り込み、どのように処理するのかを判断できます。この設問をする際には「さらに7を引くと?」というように質問していくことで作動記憶の評価にもつながります。
設問5:言葉の遅延再生
この設問では、設問3で記憶した言葉を呼び起こせるか(想起できるか)を判断できます。記憶の保持・想起ができるかどうかで評価が変わります。認知症がある場合には、この遅延再生ができなくなっている場合がほとんどです。
設問6:物品呼称
用意しておいた物品を見ながら、自分の目にしたものを記憶し正しい名称が言えるかどうかで即時記憶ができるかどうかと想起できるかどうかの判断につながります。
設問7:復唱
この設問でも記憶に関する判断をします。相手の言葉を正しく記憶できるかを診て、即時記憶を評価します。口頭でゆっくりはっきりと言い、一度で正確に答えられたら正解となります。
設問8:口頭での3段階命令
口頭で3つの指示をして、それを理解できるかどうかを判断する設問です。この設問は認知症となっていたり、認知機能の低下が著しかったりすると非常に難しい設問となります。指示ごとに正確に作業できれば1点ずつ加算されます。
設問9:書字の理解、指示
書いてある文字の理解と指示に対して実行できるかどうかを判断できます。文章を理解するための理解力と実行するための行動力があるかを評価します。
設問10:自発書字
自由に文章を書いてもらう設問です。認知症になると文章を構成する能力が低下することが多くあります。そのため、文章の構成能力がどの程度あるのかをこの設問で判断します。例文を与えずに文章が意味を成している場合は正解です。読み手が理解できる文章となっているかどうかが大切なので、文章でなく名称のみの場合には点数は加算されません。
設問11:図形の描写
図形の描写をすることで空間認知能力を判断できます。アルツハイマー型認知症が高度になっていたり、レビー小脳体型認知症になっていたりする場合には図形の描写が非常に困難となります。もし手指がふるえていてもMMSEの検査としては問題ないので、図形の描写ができているかどうかで判断します。
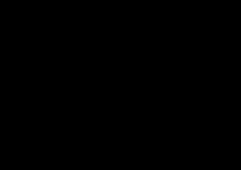
MMSEの採点とカットオフ値
MMSEは30点満点です。カットオフ値といわれる「認知症の疑いがあるかどうかを判断するライン」があります。
採点については、設問1、2、4が5点満点、設問3、5、8が3点満点、設問6が2点満点、設問7、9、10、11が1点です。ここからは、カットオフ値に対しての評価について詳しく解説していきます。
27~30点 異常なし
「認知症の疑いなし」の状態です。ただし、あくまでもスクリーニング検査ですので実際の生活に影響があったり不安を抱えたりするようであれば、脳のCTやMRIなどのより詳しい検査をおすすめします。
22~26点 軽度認知症の疑いあり
「軽度認知症の疑いがある」という判断です。早期治療のためにも正確な診断を受けましょう。軽度の認知症は早期発見できれば、その分早期治療も可能です。現段階では認知症は完治しないとされていますが、進行を遅らせることはできます。
21点以下 どちらかというと認知症の疑いが強い
認知症がない方であれば、MMSEで21点以下をとることはほぼないといってもいいです。つまり21点以下ということは認知症の疑いが強いということになります。病院や診療所でそのまま認知症の詳しい検査や診断を進めていくようにしましょう。
MMSEのデメリットは「学歴」や「職歴」に左右されること
MMSEは手軽に認知症の疑いがあるかどうかを調べられる点で便利なテストです。また「世界で最も使われている」という点で信頼性があります。そのほか、先述した杉下教授によって、妥当性や信頼性が検証されています。
出典:J-STAGE「 MMSEJ(精神状態短時間検査―日本版)の妥当性と信頼性について : A preliminary report 」しかしMMSEにもデメリットがあります。「記述式」ですので、識字する能力によっては正しい結果が出ないことです。認知機能に問題がなくても、学歴や職歴によっては、記述ができない可能性があります。
MMSE以外の認知症スクリーニング検査
MMSEは世界で最も使われている一般的な認知症スクリーニング検査ですが、そのほかにも検査方法はあります。
長谷川式認知症スケール(HDS-R)
日本人の長谷川和夫氏が作った認知症のスクリーニング検査です。以下の9つの設問に答えることで認知症の疑いがあるかを判断します。
長谷川式認知症スケール(HDS-R)の質問項目
- お歳はいくつですか?
- 今日は何年、何月、何日ですか? 何曜日ですか?
- 私たちが今いるところはどこですか?
- これから言う3つの言葉を言ってみてください。あとでまた聞きますので、よく覚えておいてください。(以下の1または2の単語を言う)
1:桜・猫・電車/2:梅・犬・自動車 - 100から7を順番に引いてください。100引く7は? それからまた7を引くと?
- 私がこれから言う数字を逆から言ってください。「6-8-2」「3-5-2-9」
- 先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください。
1:桜・猫・電車/2:梅・犬・自動車 - これから5つの品物を見せます。それを隠しますので何があったか言ってください。
(時計・鍵・タバコ・ペン・硬貨など必ず相互に無関係なもの見せる) - 知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください。
長谷川式認知症スケールはMMSEと比べると記憶力の分野を重点的に見ていくのが特徴です。また記述ではなく会話形式でおこなうため、識字できない方でも受けられます。
Mini-Cog
Mini-CogもMMSEと同様に広く使われているテストです。言葉の記憶、時計描画、といった項目で認知症の疑いを調べます。2分以内で終わる簡易的なテストです。
MoCA(Montreal Cognitive Assessment)、コース立方体組み合わせテスト
MoCAやコース立方体組み合わせテストは「軽度認知障害(MCI)」の疑いを見つけるテストです。軽度認知障害とは認知症に進んでいく途中の状態といわれています。つまり「なにかおかしい」と感じた際に試すことで早期発見・早期治療につながる可能性があるスクリーニングテストです。
認知症に対する家族の心構え
実際にMMSEなどの認知症評価ツールを用いたうえで、病院で認知症と診断を受けるかもしれません。その際に家族として必要な心構えについて紹介します。
協力者をつくって相談する
介護はストレスが掛かるものです。特に認知症の方の介護は意思の疎通をしにくいため、コミュニケーションを取るだけでもイライラしてしまうことがあります。
その際は、周りの家族や友人といった親しい関係の人に介護の悩みを打ち明けて相談をするようにしましょう。「愚痴をこぼせる間柄の人」がいるだけで、気持ちが楽になりますし、前向きに介護に取り組めます。
ショートステイを使って息抜きをする
ショートステイとは介護保険サービスの一つです。数日~2週間程度にわたって介護施設に入居し、施設入居と同じサービスを受けながら暮らします。
認知症が進行すると、介護者はほぼつきっきりで面倒をみなくてはならないケースも多く、気が休まりません。そんなときはショートステイを利用して要介護の方のお世話を任せることで、リフレッシュができます。ショートステイの使い方については以下の記事を参考にしてみてください。
介護施設入居を検討する
もし重度の認知症まで進行した場合は、介護施設への入居を検討するのも一つの手です。生活全般の介護を施設に任せることで、自宅での介護の負担がなくなります。介護を受ける方にとっても、高品質なサービスを受けられて生活がより充実するという場合もあるのです。
疑いがある際は病院を受診すべき
認知症の疑いがある場合には、必ず病院に行って「認知症かどうかの検査」をすることをおすすめします。ただ、その場合には本人に納得してもらって病院へ行き検査に協力してもらう必要があります。自身が認知症かもしれないと家族から言われたら、自分だったらどう感じるかをしっかりと考えながら本人と向き合うようにしましょう。
MMSEは質問形式での検査のため、実施する際には質問内容をアレンジせずに本人の体調が良い時におこなう必要があります。万が一、体調不良時や精神的に不安定な場合には、精神状態によって点数が低くなってしまう可能性があるためです。
不安が多い時には、まずは専門家に相談してみることが大切です。さらにCTやMRIなどの脳の検査、MMSE以外の認知機能に関する検査、生活状況や生活歴などから認知症かどうか、また認知症であった場合どのような認知症なのかを診断してもらいましょう。早期に発見することで早期治療につながり、認知症の進行を遅らせることができます。
疑いを持って検査することは重要ですが、MMSEなどの認知症に関する検査をした後のフォローも非常に大切となります。気にしているようには見えていなくても、実際は大きな不安・絶望を抱えている場合があります。
認知症と判断された場合「最近物忘れが激しかったのも認知症のせいだったのか」と割り切れればいいかもしれません。しかし、認知症を自覚することで今後の生活についての不安は大きくなります。本人が特に気にしていないような素振りがあっても、それを鵜呑みにせずなるべく本人が安心できるように配慮していくことが大切です。
MMSEはあくまで「疑いの有無」を判断するもの
MMSEは、認知症の疑いがあるかどうかを簡単に検査できる評価項目となっています。現在、広く流用されており実際の医療現場でもよく用いられている検査方法でもあるので、MMSEと聞いて不安になることはありません。
「疑いが強いかどうか」を判断するための検査のため、正確な診断や検査をおこなわない限り認知症であるという診断はつきません。本人や家族同士でMMSEをおこなうことも可能ですが、より客観的な立場から検査すること、また検査結果によってはそのままより詳しい検査にスムーズに移行するために医療機関や専門家にMMSEを実施してもらいましょう。
年齢を重ねればある程度記憶力が低下したり、判断力が低下したりすることは誰にでも起こり得ます。生活状況にどの程度影響があるのかも認知症の判断基準となってくるので、本人の協力だけでなく家族の協力も不可欠となるでしょう。
認知症は、早期発見できればその分早期治療をおこない症状を遅らせることができます。気になることがあれば相手の気持ちに配慮しつつ、検査を受けてもらうように促していきましょう。
-
関東 [4771]
-
北海道・東北 [2431]
-
東海 [1651]
-
信越・北陸 [1002]
-
関西 [2392]
-
中国 [1153]
-
四国 [722]
-
九州・沖縄 [2389]
この記事のまとめ
- MMSEは専門家に相談して実施する
- 検査を受ける本人の気持ちに配慮する
- 検査後のアフターケアも大切
豊富な施設からご予算などご要望に沿った施設をプロの入居相談員がご紹介します